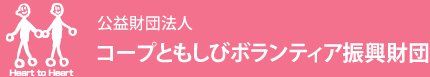一ノ間麻紀さんのお話
BONBONCANDY(ぼんぼんきゃんでぃ)にじいろじかん 理事
深刻な不安を抱える
病気の子どもたちに
豊かな未来を実現させたい
ともしび財団では協賛企業やコープこうべとともに社会的課題の解決に
意欲的な市民団体を応援する「やさしさにありがとう ひょうごプロジェクト」
を実施しています。今年度の助成団体である[BONBONCANDYにじいろじかん]は
我が子の闘病経験をもつ母親とすべての子どもたちへのやさしい未来を願う
母親が集い、子どもの遊びイベントや家族の支援活動を行っています。
理事の一ノ間麻紀さんにお話をお聞きしました。

保育士として保育園や幼稚園で勤
めた後、小児科病棟の病棟保育士
として病気と闘う子どもたちと2年過ごす。
翌年に出産、4年後我が子の病気が発覚。
闘病生活を送る中であらためて
「治療中の子どもたちや家族に大切
なことは笑顔で過ごすことであり
決して子どもの遊びをあきらめて
はいけない!」と同じ想いを持つ
母親達と[BONBONCANDYにじいろじかん]を
立ち上げる。
子どもにとって遊ぶことは
生きることそのもの
がんは高齢になるほど増えてくる病気ですが、ごく少数の割合で子どもに発症することがあります。その小児がんでもっとも多いのが血液がんの一種、急性リンパ性白血病で、私の娘は4歳のとき、この病気が判明しました。ちょうど自営業をやり始め、子どもを保育園に預けるなどバタバタと忙しい日々を過ごしていたので、「今日からママはお仕事を辞めて、病院で一緒に過ごすことになるよ」と言うと、ママを独占できると思ったのか、とまどいながらも嬉しそうだったのがやりきれなかったですね。
私は小児科病棟の保育士として働いた経験があり、子どもの白血病は治療成績がよく、治せる病気であることや当時の看護師さんに相談させてもらうなど情報を得ていたので、ほかのお母さんよりはかなり救われていたと思います。治療がスムーズに進み、4か月後に退院を迎えることができたとき、「やっとここから抜け出せる、これから楽しい生活が始まるんだ」と期待に胸を膨らませましたが、待っていたのは厳しい現実でした。引き続き自宅での抗がん剤服薬治療の影響で、娘の免疫力はとても低く、菌やウイルスを寄せつけないためには感染対策を徹底しないといけません。つねに消毒薬を持ち歩き、調理ではナマモノの扱いに注意し、人との接触を避け、夜に買い物に行くなど、家に閉じこもる生活が続きました。入院中には予想もしなかった孤独やプレッシャーを退院後に思い知らされましたね。
そんな私をなぐさめてくれたのが同じ病気の子どもをもつママたちでした。なかなか人には言えないつらい体験を語り合うことで気持ちが癒され、元気をもらうことができます。ママたちと情報交換するなかで、病気の子どもたちが遊べる場所をつくりたいねという話題になりました。とくに入院中は体に負担のかかる治療が行われるので、遊びをあきらめてしまい、子どもから笑顔が減ります。子どもにとって遊ぶことは生きることそのもので、子どもらしくいられる時間はいましかありません。私は退院後の子どもが安心して遊べる場所を探しましたがなかなか見つからず、インスタでも問いかけてみたところ、大阪の[※TSURUMI こどもホスピス]について教えてもらうことができました。しかし娘は保育園に復帰することになっていたので、利用は叶いませんでしたが、子どもの尊厳を大切にする取り組みにおおいに共感しました。自分たちもそのような場所づくりをめざそうと2020年3月[BONBONCANDYにじいろじかん](略:ぼんきゃん)の活動が始まりました。
小児がんのつらい経験を
未来をよくする力に変えたい
ぼんきゃんでは、退院後の子どもが偏見にさらされず、リラックスしながら楽しめる草花遊び会を開催しています。既製のおもちゃにはない発見や感触、香りを体験し、ちぎったり、すりつぶすなど指先をたくさん使うことで五感を刺激し、心のケアを図ります。病気でない人も参加できるので、病気への正しい理解につながればと思います。子どもの表現を尊重するアートイベントや病院内でも遊べるアートキットのプレゼントも実施しています。
私たちの遊びでは必ず、オリジナル紙芝居『ミケまるとトラきち』を観てもらっています。ストーリーは闘病をしていてもしていなくても、同じ時間を違う場所で過ごしたお友達が互いに敬意を払うという内容で「自分と異なるものをそのまま受け入れる」やさしい社会であってほしいという思いを込めています。
家族の支援活動においては小児がん経験者の家族とWEB座談会を実施し、情報の共有を強化したいと考えています。長期付き添い入院等による子どもの発達やほかのきょうだいのケア、仕事との両立などさまざまな不安や悩みに寄り添い、いま頑張っている家族に手を差し伸べ、小児がんのつらい経験をできるだけポジティブに変換することで未来をもっとよくする力に変えたいと願っています。退院後も寄り添えるコミュニティの実現をめざしていきたいですね。
※TSURUMI こどもホスピス/生命を脅かす病気の子どもの学び、遊び、憩い、やってみたいと思うことを叶え、その子の「生きる」を支えるための「第2のわが家」を理念とする活動。
TOPへもどる
2022年度 ボランティア活動助成募集のお知らせ→助成説明会は終了しました
ボランティア活動助成は、市民がお互いに支え合い、やさしさと思いやりに満ちた地域社会の形成を目指すボランティア団体(個人)を応援する助成を行っています。
コロナ禍で活動を継続している団体(個人)を引き続き支援したいという思いから、助成対象となる経費(食材費・交通費など)を大幅に拡大し、助成総額を増額します。
ご応募お待ちしております。
募集期間 2021年10月1日(金)~12月28日(火) 17時 郵送必着
【助成総額】1,300万円
【助成対象団体】県内で公益的な活動を行う法人格を持たないボランティア団体(個人)
2022年度ボランティア活動助成 募集と助成説明会のお知らせ(A3中折)
→ 助成説明会は終了しました。
<応募方法>
新規で申請を希望する団体(個人)は必ず「2022年度ボランティア活動助成説明会」に参加後、当財団まで郵送にて申請書をお送りください。
ともしび助成
募集要項
申請書 Word版/Excel版
申請書(記入時の注意事項)
きらり助成
募集要項
申請書 Word版/PDF版
申請書【記入例】
問い合わせ・申込み
(公財)コープともしびボランティア振興財団
電話:078-412-3930 FAX:078-412-3871
TOPへもどる
第3回高校生ともしびボランティア顕彰(アワード)募集→締切りました
ともしび財団では高校生の心豊かな育ちとボランティア人材の育成を願い、2019年度より「高校生ともしびボランティア顕彰(アワード)」を実施しています。
第3回となる今回は、今まで行ってきた活動や近年の状況に合わせて新たに始めた活動など、幅広い分野で活躍している高校生ボランティアを募集します。
たくさんのご応募お待ちしております!!
◆応募資格
兵庫県下の高等学校(全日制・定時制・通信制の高等学校、高等専門学校、中等教育校、養護学校高等部フリースクール等)に在籍する生徒の皆さんによる、非営利のボランティア活動を行う生徒会や部活動、委員会、サークルなど学校に認定された団体であること。
※授業としての申請は対象外です。また、1校につき1団体の応募に限ります。
※主な活動以外にボランティア活動を行っている団体も応募可能です。
(野球部による地域清掃活動など)
※中高一貫校からの応募の場合は、中学生もご参加いただけます。
※在校生であれば、年齢の上限はありません。
※複数校で構成される団体も応募可能ですが、その場合は監督者が構成校の教員である
ことが条件です。
※既に当財団の助成を受けている団体や昨年度の顕彰団体も、応募可能です。
◆顕彰団体数
15団体程度
◆賞
・顕彰状
・副賞(1団体につき、30,000円)
※副賞の用途について財団への報告は不要です。
◆選考基準
地域や対象者の暮らしを良くすることにつながるボランティア活動や社会貢献活動を主体的に行っていること。
<選考のポイント> ① 社会貢献度 ② 創意工夫 ③学んだこと、感じたこと などを総合的に判断します。
◆選考方法
申請書受付後に選考基準に基づき、選考委員会にて緩やかな選考を行い、顕彰団体を決定いたします。
◆応募期間
2021年9月20日(月)~2021年11月15日(月) 17時郵送必着
◆スケジュール
・9月20日~11月15日 応募受付
・12月上旬 選考委員会にて申請書を選考
・12月下旬 顕彰決定のお知らせ
※選考理由についてのお問い合わせには応じかねますので、予めご了承ください。
◆顕彰決定後について
・交流や発表の機会を設ける予定ですので(2022年3月~4月頃実施予定)
可能であればご参加ください。
・ご希望に応じて、下記のようなサポートを行います。
財団が助成している団体との交流
財団ホームページにて活動内容をご紹介 など
◆応募方法
指定の申請書に必要事項を記載のうえ、下記宛に郵送にてお送りください。(メールでの送付は不可)
※必ず学校長・指導教員の了承を得てご応募ください。
※顕彰団体に対し、財団からの取材や財団ホームページ・広報物へ活動内容および写真
の掲載など依頼する場合があります。
※一度ご提出いただいた申請書の返却・差し替えはできません。
※申請書は黒インクか黒ボールペン、又はパソコン入力等で記入してください。
※申請書のご提出前に、必ずコピーをとり、手元に保管しておいてください。
(申請内容について、お問い合わせする事があります。)
※受付締切日17時以降に受付することはできませんので、ご注意ください。
※応募に際しご提出いただいた情報は、本顕彰制度をはじめとする活動支援事業以外の
目的では使用いたしません。
◆申請書の送付先および問い合わせ先
〒658-0081 神戸市東灘区田中町5丁目3-20 生活文化センター西館2F
(公財)コープともしびボランティア振興財団 「第3回 高校生ともしびボランティア顕彰(アワード)」事務局 宛て
※封筒の表書きに 「第3回 高校生ともしびボランティア顕彰(アワード)申請書」 と
明記してください。
TEL:078-412-3930 (土日祝、年末年始を除く、10:00~17:00)
・募集要項のダウンロードはこちら
・申請書のダウンロードはこちら PDF版/Word版
・チラシのダウンロードはこちら
<後援>兵庫県教育委員会・兵庫県私立中学高等学校連合会
TOPへもどる
前田裕保さんのちょっといい話
コープこうべ地域活動推進部 拠点づくり推進 統括 (現 第1地区本部 本部長)
社会的課題の解決と地域の
居場所づくりで誰もが
暮らしやすい社会の実現をめざす

1989年灘神戸生協(現コープこうべ)へ
入所後、宅配事業一筋。2014年宅配事業部
訪問供給サポート、拠点づくり推進部などを
経て現職。社会課題が多様化する中、公益
性の高い活動を行う地域諸団体とつなが
り、その団体の活動を支援する。「私自身は
DV支援員や炊き出しのお手伝い、伴走ボラ
ンティアなどをやっています。ランニングが
日課となり、いつの間にか適正体重に(笑)。
誰かのために走ることで長続きしますね」
ともしび財団では「若者のボランティア人材育成」をめざして高校生の
ボランティア活動を顕彰しています。
その顕彰団体のひとつでもある「県立尼崎西高等学校ボランティア部」は
コープこうべの居場所事業「大庄元気むら」で、地域と協力した多世代交流を
行っています。
居場所事業などの地域活動に携わる前田裕保さんにお話をお聞きしました。
地域の居場所は
ひとや社会を幸せにする
昨年12月、尼崎の大庄地区住民と尼崎西高校による合同文化祭が
「大庄元気むら」で開催され、全国でもあまり例のないものとして大きな
反響をいただきました。
「大庄元気むら」は地域活動推進部が手がける居場所のひとつ。
コープこうべの居場所事業は、2014年に宅配事業の傘下で立ち上がった
「超高齢社会における必要なしくみを構築する」というプロジェクトチームが
始まりです。
それまで宅配事業一筋だった私は突然このテーマと向き合うことになりました。
「超高齢社会の問題は〈健康、孤立、経済〉の3つの不安要素に集約されること。
その解決策として人が集い、不安や困りごとを相談できる場が必要である。
コープこうべには150ほどの店舗があるので、店内の空きスペースを利用すれば
地域の居場所づくりが可能」という提案をすると、なんと私が居場所事業の担当者に。
生協には社会的課題の解決をめざすという命題もあることから、居場所づくりを
しながら社会的課題を解決していくという事業がスタートしました。
居場所事業は店舗の空きスペースや地域のフリースペースを利用し、地域の人たちが
いきいきと過ごせる場の創生を目的としています。
主役はあくまでも地域住民、私たちは見守りに徹することを心がけています。
居場所の設定は高齢化が進んでいるエリアをターゲットに現地をリサーチするところ
から始まります。地域にアンテナを張ると「ここをなんとかしたい」という世話好きな
人が見つかるものです。そんな地域愛にあふれる人がさらに人を呼び、多様な社会的
課題の団体ともつながっていくので、支援と共感の輪が広がりますね。
尼崎の大庄地区は高齢者と単身者の割合が高いエリアで、2017年から調査をして
いました。閉店予定だったコープ大庄を改装し、2019年11月コミュニティスペース
「大庄元気むら」がオープン。
地域の活性化には若い力も必要と考え、地元の学校に声をかけたところ、尼崎西高校
ボランティア部が手を挙げてくれました。
会議の場に高校生がいるとこれまでにないアイデアが飛び出し、みんなが元気に
なります。地域で何かしたいという話題になったとき、「コロナで中止になった文化祭
を地域の人に見てもらえたらいいね」と盛り上がり合同文化祭に結びついたんです。
コロナ禍で開催が危ぶまれましたが、動画やZoom配信を取り入れるなど対策を
徹底し実現できたのは大きな成果でした。
ハッピーな話題はそれだけではありません。高校生が地域の大人と触れ合うことで
進路を決めるきっかけを得たり、孤独な高齢男性がここで知り合いが増え生きがいを
持てたなど、居場所がもたらすパワーのすごさを実感しています。
不平等な社会を変えることが
コープこうべの使命
社会的課題については実態を把握するため、いろいろな市民団体を訪ねました。
最初に出会ったのはシングルマザーを支援する団体で、シングルマザーになった要因が
夫の自死やDVによるケースも少なくなく、体験談を聞いたときのショックは
今も忘れません。
日本では毎年約2万人が自殺し、それをコープこうべの店舗利用者にあてはめると
1店舗あたり毎年2人が亡くなる計算になるんです。
DVはニュースで聞く遠い出来事のように思っていましたが、兵庫県は人口あたりの
DV被害者が全国でも多い地域だそうです。
その他にも子どもの貧困や不登校、孤独な子育てに悩むお母さんの現実も知りました。
今の時代は誰もがセーフティネットから抜け落ちやすく、それを救えない社会である
ことに気づかされたんです。
その一方で世間の偏見や差別意識の根深さも知りました。
本来であれば被害者であり、守られるべき人たちが、逆に責められることもある
そうです。生きづらさを抱える人たちへのアプローチだけでなく、偏見や差別を
なくしていく努力も大切なことですね。
暮らしを守り、健全な社会をめざすことがコープこうべの使命と考え、これからも
活動に邁進したいと思います。
TOPへもどる
2021年度コロナ禍でのボランティア活動についてのアンケート結果について
2020年の新型コロナウイルス感染症拡大から1年を経て、助成するボランティアグループの活動状況の把握や、今後の発展に向けた支援を検討するため、2021年度の助成先(148グループ)にアンケートを実施しました。
アンケート結果の詳細についてはこちらをご覧ください。
TOPへもどる
第5回「やさしさにありがとう ひょうごプロジェクト」助成団体 決定
脇原隆司さんのちょっといい話
特定非営利活動法人 兵庫セルプセンター事務局長兼事業企画部長
障がいがある人の仕事を全力サポート
豊かな人生を地域とともに

大学卒業後、一般企業にて企画営業職に
従事。2008年NPO法人兵庫セルプ
センターに入職。兵庫県、神戸市の
共同受注窓口事業の他、障害福祉事業所が
製造する商品(菓子)のレベルアップと
販路拡大を目指すコンテスト「スウィーツ甲子園」
兵庫県内の事業所商品の販売サイト
「+NUKUMORI」等の事業を担当。
チャリティーバザーなどで障がいがある人たちの手作り品を見かけたことは
ありませんか。温かみを感じる素朴さと本物志向が持ち味で、
ファンも多いようです。そんな障害福祉事業所のモノづくりを全力サポート
する兵庫セルプセンターの脇原隆司さんにお話を聞きました。
働く願いと事業所の元気を
社会につなげよう
障害福祉事業所の商品はおもにバザーやお祭りなどの地域のイベントで販売
されています。それらが売り上げの多くを占めているのですが、新型コロナ
ウイルスの影響でイベントが中止になり、販売の機会が失われてしまいました。
そんななか、コープこうべに協力をいただき、「つながるマルシェ」という
販売会が各店舗で実現(2021年2、3月)。地域とともに生きる人たちの
つながりだけでなく、自分たちの商品が近所のコープで売られるという喜びと
やりがいが感じられたうれしい取り組みになりました。
兵庫セルプセンターとは障害福祉サービス事業所の仕事を支援する組織で
そのような団体は全国に存在します。兵庫県の場合、平成13年に兵庫県社会就労
センター協議会が授産活動活性化事業を始め、さらに活動を充実させるため、
平成16年に当センターが発足。
「障がいがある人たちの働く願いと事業所の元気を社会につなぐ」を合言葉に、
障害福祉事業所の〝働く〞に関わるさまざまな支援を行っています。
なぜ支援が必要なのかというと事業所での仕事は工賃が低く、自立生活が
難しいという現実があるからです。とくにモノづくり(授産)においては
体制が脆弱です。そのためセンターでは問題解決に向けて障害福祉サービス
事業所の販路拡大につながるさまざまな事業を展開しています。
「買ってください」から
「選んでうれしい」商品を
たとえば、事業所でクッキーを作ることになった場合、支援者にクッキーづくり
の得意な人がいて、事業に踏み切るケースが多いと聞いています。
大量生産や機械化をめざしているわけではないので、ハウスメイドの延長です。
障がいのある人が仕事のどこを分担するかは事業所には福祉のプロがいるので、
それぞれで工夫されますが、問題なのは商品の企画や営業が得意ではないことです。
企業ならお客さんが買いたくなるような製品戦略は当たり前なのかもしれませんが、
事業所の状況は少し違います。
吟味した材料を使い、手作りで丁寧に仕上げた商品でも、その魅力を伝えるという
ところが企業ほど上手ではありません。そこで私たちはどのようにすれば、もっと
クッキーが売れ、工賃アップにつながるか、事業所と一緒に考えます。
専門家とのマッチングにより、事業所の技術力・商品開発力等のスキルアップを
めざしたり、プロの手を借りて、デザイン性にすぐれたパッケージを企画するなど、
製品戦略のお手伝いもします。
そのような取り組みの結果、最近では一般と比べても引けを取らない商品が増え、
おいしさだけでなく、「人にも勧めたい」「クラウドファンディングみたいで
うれしい」と評判を呼んでいます。
なかでもお菓子の品質向上と販路拡大をめざすコンテストの「スウィーツ甲子園」は
平成21年度から実施していますが、商品のレベルアップには目を見張るものが
あります。地元の農産物を使うだけでなく、乳製品や酒造メーカーと共同で
開発するなど、地域連携のユニークな商品が話題になっています。
今後も地域とのつながりをこれまで以上に作っていきたいと考えています。
地元企業の困りごとや地域の課題を福祉の側で担うことができれば、仕事開拓になる
だけでなく、地域の活性化に貢献できるかもしれません。
地域と福祉をつなげる企画はまだまだありそうです。
また、コロナ禍における販売方法としてインターネットショッピングにも力を入れたい
と思っています。
すでに兵庫県の委託による「+NUKUMORI(ぷらす ぬくもり)」というサイトを
当センターが運営していますが、販売に特化した内容にとどまっています。
事業所独自のサイトがあれば、頑張っている姿やモノづくりのメッセージを発信でき、
お客さんの声もダイレクトに聞くことができます。そのようなサイトの立ち上げにも
支援していきたいですね。
TOPへもどる
第2回高校生ともしびボランティア顕彰(アワード)顕彰団体決定
「若者のボランティア人材の育成」を実現すべく昨年度よりスタートした
「高校生ともしびボランティア顕彰(アワード)」。
2020年12月に開催した選考委員会にて、顕彰団体を決定いたしました。
どの団体も地域や困っている人たちのため、高校生らしい若さに溢れた
素晴らしい活動を行っていました。特にコロナ禍においても活動を止める
ことなく、活動内容を変化させたり、新たな活動を模索しようとする
前向きな姿勢が印象的でした。
財団では今後も、高校生がボランティア活動を通して、心豊かに成長し
次世代の担い手となることを願うとともに、その活動が世代を超えた
ネットワーク形成へとつながることを目指して、高校生のボランティア活動を
応援していきます。
<第2回高校生ともしびボランティア顕彰(アワード)顕彰団体>
・学校法人芦屋学園 芦屋学園高等学校 ボランティア部
・学校法人甲南学園 甲南高等学校 ボランティア委員会
・学校法人神戸女学院 神戸女学院中学部・高等学部 雫の会
・学校法人神戸創志学園 クラーク記念国際高等学校 芦屋キャンパス 地域研究部
・学校法人淳心学院 淳心学院中学校・高等学校 淳心学院中・高ボランティアチーム
・学校法人玉田学園 神戸常盤女子高等学校 ボランティア部
・兵庫県立 明石清水高等学校 ボランティア部
・兵庫県立 明石南高等学校 めいなん防災ジュニアリーダーMRDP
・兵庫県立 芦屋高等学校 ボランティア部
・兵庫県立 尼崎西高等学校 ふるさと貢献 大庄元気むら
・兵庫県立 伊川谷高等学校 ボランティア部
・兵庫県立 柏原高等学校 インターアクト部
・兵庫県立 松陽高等学校 SDGs Project Team
・兵庫県立 東播工業高等学校 空飛ぶ車いすサークル
・兵庫県立 豊岡総合高等学校 インターアクトクラブ
・兵庫県立 西宮今津高等学校 ING部
・兵庫県立 舞子高等学校 天文気象部
※五十音順
TOPへもどる
宇津井英輝さんのちょっといい話
コープこうべ供給事業本部 買い物支援 統括
「移動店舗」や「買いもん行こカー」で
買い物ができる当たりまえの暮らしを

2003年契約職員として入所、06年
総合職員に登用。協同購入センター三木
協同購入センター丹波、宅配事業部
電力事業TF、協同購入センター但馬、電力事業
を経て、現職。「20代の頃、仕事で悩んでいた
私を力強く励ましてくれた友人がいました。
コープ職員だったその彼の見ていた世界が
見たくて30歳のとき自分もコープこうべへ。
組合員さんの温かさや信頼関係は彼の言葉
どおりでした。この感動は私の宝物です」
少子高齢化や地域事情などで、日常の買い物ができなくなってしまった人を
「買い物困難者」といいます。交通手段がない、足腰が弱ったなどで買い物が
困難になる事態は誰にでも起こりうること。他人事ではありません。
コープこうべではそのようなお困りの対策として、さまざまな買い物支援事業
を行っています。担当の宇津井英輝さんにお聞きしました。
移動店舗が
地域コミュニティに貢献
いつの時代も日常の買い物に不便を感じる人は存在したでしょう。
しかしそれが「買い物難民」という社会現象としてクローズアップされたのは
今から15年以上前のことで、ある報告により、高齢者が買い物困難に強いられている
「見えない実態」が浮き彫りになりました。
人口減に伴い、路線バスなどの公共交通機関の減少や高齢者の免許返納などで
移動手段を失うことが要因のひとつと考えられ、買い物に困る高齢者はさらに増加
する見通しです。農林水産省は「店舗まで直線距離で500m以上、かつ、65歳以上で
移動手段を持たない人」を「買い物困難者」と定義しており、地方だけでなく
「オールドタウン化」した都市部での増加も顕著になっています。
想像してみてください。往復1㎞以上、その片道を重い荷物を持って歩くのです…
雨の日も寒い日も。若い人でもしんどいですね。買い物困難によるダメージはそれだけ
ではありません。外出するために服装を整え、近所の人とコミュニケーションをとる
などの暮らしのうるおいも失われてしまうのです。とくに女性は買い物を好まれ、実物
を手に取って確かめたいという方が多いので、買い物ができない苦痛は相当なものだと思います。
コープこうべでは買い物困難の課題に対処すべく、2011年に「移動店舗」をスタート
させました。これは専用車両に生鮮食料品などを積み、決まった場所(停留所)に
週1回、同じ曜日、同じ時間に運行するシステムで、現在、9台が約520カ所/週の
停留所を訪問。約2500人/週が利用されています。車は2トントラックと軽自動車の
2タイプで、2トン車は約800品目を積み、中山間部をエリアとする一方、軽自動車は
約400品目を積み、小回りの利く住宅地を運行しています。
ドライバーは地域や曜日による売れ筋を把握しているので「今日は刺身がよく出るだ
ろうから、多めに揃えておこう」など、ニーズに合わせた品目をその日の朝、新鮮な
状態で積み込みます。
移動店舗は地域から「うちに来てほしい」という要望が強く、小野市市場地区の場合は
行政との3者協定のもと、自治会が中心となり、スタートしました。
事前に自治会が約3,000軒にアンケートをとり、利用したい住民マップをもとに停留所を
決定。地域の愛唱歌を流して到着を知らせ、声をかけあいながら集まってこられるので
停留所はいつも大にぎわいです。自治会の役員さんがお年寄りの介助や袋詰めの手伝い
をされたり、机やいすを出して井戸端会議を楽しむなど、買い物から広がるコミュニ
ティには目を見張るものがあります。
小野市をモデルに、神戸市西区美穂が丘でも同様の取り組みを行っています。
喜びの声が続々!
買い物による相乗効果も
買い物支援の取り組みとして今、もっとも注目されているのが乗り合いタクシー方式の
「買いもん行こカー」です。コープデイズ神戸北町を擁するエリアは坂道が多く、
買い物にお困りの組合員さんが多かったことから、2016年10月に事業がスタート。
店舗から車で20分圏内にお住まいの65歳以上か、障がい者手帳を所有、あるいは
未就学児をもつ組合員さんを対象に自宅までの往復を無料送迎します。
8人乗りのミニバンで巡回し、店舗で約60分買い物をしていただく間に、別のエリアの
組合員さんをピストン送迎するので、車の稼働にロスがないことと、移動店舗のように
車両を改造する必要がないため、展開しやすい事業といえます。
現在、19店舗で17台が運行し、約2,150人が登録されています。
平均年齢は80.1歳、ほぼ女性です。「夫が病気で倒れ、車の運転ができなくなり途方に
暮れていた。本当にありがたい」「運転手さんをはじめ、みなさんと乗るのが楽しい」
など喜びの声が多く寄せられています。独居利用者の安否確認や利用者さんたちの
絆づくりにも役立っています。
また、現在はコロナ禍により行っていませんが、高齢者施設の入居者を「買いもん
行こカー」でお連れし、ボランティアが付き添う「ショッピングリハビリ」では
普段じっとしている方が買い物で歩き回り、生き生きとした表情を見せるなど
リハビリ効果もてきめんです。
これからもみなさんのお役に立つ、買い物支援事業の充実に務めていきます。
TOPへもどる