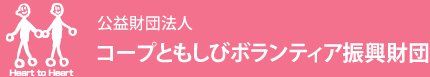濱田理恵さんのちょっといい話
2024年10月発行/第121号
特定非営利活動法人 ゆるり家代表
濱田理恵さんのちょっといい話
地域の『コドモ』を見守る
気のいい『オトナ』で
あふれるまちを

濱田 理恵(はまだ りえ)さん
兵庫県加古郡稲美町在住。社会人の娘、息子の母。現在は夫、ネコ3匹と暮らす。2000年に子育てサークル[はらっぱ]を結成。その後、2009年に[みんなのお茶の間 ゆるり家]を開設。2024年2月特定非営利活動法人化。稲美町こどもの居場所づくり支援事業として今年の2学期から2つの町立中学校で校内居場所を開設。
よその地域にはあるけど、地元の町にはない……それなら、自分たちで作っていこうとさまざまな子育て支援やまちづくりに取り組んできた[ゆるり家]。今年、NPO法人格を取得し、さらなる活動の広がりをめざしています。代表の濱田理恵さんにお話を伺いました。
子育てママ同士の
おしゃべりに支えられた
私は大阪で生まれ、高校まで静岡(実家)で育ち、大学では心理学を専攻。京都の大手進学塾に就職し、代表秘書として働いていました。あるとき、会社宛てに「学習塾向けの不登校の研修」の案内が届きました。それに個人的に参加させてもらったことがきっかけで、担当部署に異動し、不登校の子の学習支援の仕事をしました。学習塾の中での支援に限界を感じていたとき、不登校の子どもたちのための居場所づくりの準備をしている民俗学畑の風変りな人に出会いました。その人は、子どもたちを沖縄の「おばあ」のところに連れていくなど、ユニークな取り組みを行っており、その居場所でスタッフとして働かせてもらうことになりました。結婚して稲美町に移住しても仕事は続けたかったので、出産で辞めるまでは週2日ペースで京都に通いましたね。稲美町は夫の実家があるわけではなく、たまたま手ごろな土地を勧められ、住み着いたにすぎません。こうして縁もゆかりもない土地で私の子育てが始まりました。
不安がいっぱいの子育てで私の支えになっていたのが、出産した助産院(神戸)で月1回開かれていたお母さんたちの会でした。当時、稲美町では子どもと一緒に遊ぶ会はあっても、親同士が話をするような会はありません。そこで、地元でできた友だちと一緒に、親同士でおしゃべりできる場があれば、と結成したのが[はらっぱ]でした。
子どもが大きくなってくると、仕事に出かける母親が増えていきます。私も働きたかったけれど、子どもが病気の時にみてもらえる人もいないので再就職は難しい。少し上の先輩たちが子育てサークルをNPOにして事業を受託しているところが全国的に増えていた時期だったので、そういう形で仕事にできたらいいなと思い、事業としてやっていきたい3人で[ゆるり家]を立ち上げました。
社会で子どもを育てる
ゆるり家を立ち上げようとしていた頃、私は学童保育の父母の会の会長をしていて、その時初めて学童保育の待機児童が出ました。そのため、昼間は子育て中の親子で集える子育て広場、放課後は民間の学童保育をすれば、事業として成り立つのではないかと考えました。ひとまず、待機児童は隣の学区の学童保育に受け入れてもらう段取りをつけ、保護者にお話したところ、全員から「それなら、おばあちゃんにみてもらうので結構」と言われました。この地域には民間の学童へのニーズがないことに気づき、事業化は白紙に。しかし、子どもたちの出入りOKという理想的な古民家が先に見つかっていたので、何もかも諦めるのは惜しい。そこで3人で家賃を負担し、やりたい活動を始めることにしたんです。
子どもが保護者の送迎がなくても自分の意志で自分の足で行ける場、ということで「駄菓子屋」の形をとることにして、メンバーそれぞれが仕事をしながら、駄菓子屋や子育てひろば、長期休暇中の子どもたちの体験活動の場など、子どももおとなもゆるやかに集える場をボランティアで開くことにしました。ゆるり家をはじめて1年後、我が子が不登校になったり、実母の認知症が進むなど、家庭の方もいろいろあり、子育てひろばと駄菓子屋だけを細々とやる時期が長く続きました。
ゆるり家設立10年目を迎えたとき、「こどものまち」事業を実施しました。これは子どもだけでまちを作る遊びのプログラムで、これも近隣では稲美町だけ行われていなかったんです。久しぶりに外に向けて動き始めると若い世代ともつながりができ、子育て支援の制度があっても使いにくい現状を知らされました。私たちが子育てで困っていたことが、20年近く経ってもあまり変わっていないことに愕然とし、私たち自身の責任でもあると感じました。それ以降、より社会課題を意識しながら動くことが増えています。
様々な社会課題は、喉元過ぎれば……のように、しんどい時期が落ち着くと、しんどさや理不尽なことを忘れがちですが、次の世代も同じ問題に直面しています。私自身が子育て中に出会って影響を受けた「社会で子どもを育てる」という考えを忘れず、自分事として関心を持ち続けていきたいと思います。