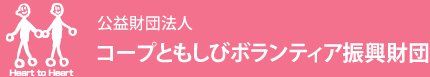西ユミ子さんのちょっといい話
2025年10月発行/第125号
まんまプロジェクト代表
西ユミ子さんのちょっといい話
思いやりのバトンを
次につなげていきましょう

西 ユミ子さん(にし ゆみこさん)
1948(昭和23)年生まれ。尼崎市在住。28年間、学校給食調理員を担う。64歳で退職後、子ども食堂[ほっとぷらっと](2016年)の立ち上げと運営に携わり、2017年子ども食堂[晴れるや]を開設(3年間、両方の子ども食堂を兼務)。2021年9月現在地でリニューアルオープン。コープこうべ虹の賞受賞、尼崎市コミュニティ活動表彰ほか。「子どもからもらった手紙は私の宝物です」
「社会に恩返し」という言葉、よく耳にするキーワードですが、他人から受けた善意を困っている誰かに役立てたいという思いには、揺るぎない強さがあるのかもしれません。西ユミ子さんは定年退職後の人生を[まんまプロジェクト]に注ぎ込む信念の人。今年度の「やさしさにありがとうひょうごプロジェクト」の助成団体に選ばれました。活動の原動力についてお聞きしました。
未来を諦めさせない
そんな社会を
私は生まれてこのかた、尼崎に住んでいます。昔は人情たっぷりのご近所づきあいがあり、小さい頃から子どもの預けあいやご飯を食べさせる光景を見てきました。振り返ると自分はいい環境で育ったなと思います。母親は料理上手な人で、いつの間にか私も料理が好きに。結婚後、子育てが一段落し、選んだのが調理員の仕事でした。尼崎市の学校給食調理員として長く勤めましたが、その頃は児童数が多く、一校で1000食以上作るのはざら。大量の食材を扱い、大きな鍋で調理し、重い食器の持ち運びを何十年も続けているうちに指が変形してしまいました。指を曲げるとすごく痛いんです。これを「指曲がり症」などといい、当時は職業病と認定されておらず、自費で治療するしかなかったんですが、そんな調理員たちに寄り添い、職業病と認定されるよう奔走してくださったのがかかりつけの整形外科医でした。裁判で勝訴し、医療費が無料になったことで、気兼ねなく治療ができました。その後、先生は亡くなられ、直接のご恩返しは不可能になりましたが、自分は定年退職したら社会奉仕したいと思いました。そんな私に「子ども食堂を立ち上げるので手伝ってほしい」と先生がおられた田島診療所(立花地区)から声がかかったんです。「はい!やらせてください」と即答しましたね。
2016年11月、子ども食堂[ほっとぷらっと]が始まりました。ほどなく、小学5年生の姉が未就学の弟、妹を連れてやってきました。朝も昼もろくに食べておらず、晩ご飯は母親が帰るまでわからないというではありませんか。私たちは「いまどき、子どもの貧困なんてあるのかな。もし存在していたら一人でも食べに来てほしい」と話していましたが、現実を突きつけられ、大きな衝撃を受けました。大人がしっかりしないといけない、子どもの未来を諦めさせない社会であってほしいと強く思いました。
子どもは地域の宝物
みんなで見守っていこう
満足に食事ができない子は私の地元、武庫地区にもいるにちがいない。そう思うと居ても立っても居られず、かたっぱしから知り合いに声をかけました。商店には食材の提供を、主婦には運営の手助けをお願いし、2017年4月、子ども食堂[晴れるや]を特別養護老人ホームのワンフロアを借り、開設。その後、コロナ禍には武庫西生涯学習プラザに移動しましたが、間借りだと準備が大変で、活動にも制限があります。そろそろ自前の拠点を持つしかないと考えましたが、やるからには失敗は許されません。準備期間中、15回ほど話し合いの場を持ち、ときどき福祉の専門家が高度な話をしてくださいましたが、私たちは子どもにご飯を食べさせたいというおせっかいなおばちゃんたち。つまるところ、スタッフが米1~2合持ち寄ればなんとかなるだろうと意気軒高でした(笑)
新しい拠点は入りやすい場所にしたい―その理想にぴったりだったのが商店の建ち並ぶ路面店でした。築63年、12年間空き家のため、廃屋同然でしたが改装すれば使えるはず。地域の皆さんからあらゆるご支援をいただき、2021年9月、開設にこぎつけました。
現在、第1、3土曜は弁当配布とフードパントリー、月2回の放課後カフェ[あくありうむ]では学生ボランティアによる勉強・遊び・会食などを実施しています。通りから子どもの姿が見えるので、ジュース・お菓子の差し入れやウォーキング中のおじいちゃんが立ち寄り、寄付してくださることもあります。「ケチャップ2本あるから、1本使って~」と駆け込むおばあちゃんもいます。そんな光景を子どもたちは目の当たりにしているので「活動できるのは地域の思いやりのおかげ。大きくなっても忘れないで」と必ず声かけします。思いやりのバトンを次につなげていってほしいものです。
また、活動を通して同年齢の横のつながりや異年齢の縦のつながりができるので、それが子どもたちにいい影響を与えています。たとえば、誰かが悩んでいると周りが「君だけじゃない」「次はこうしたらいいよ」と言い、悩んでいた子の顔がすっきりします。子どもの力はすごいなと思います。
ここは子育て相談や買い物中の休憩、赤ちゃんのおむつ替えも大歓迎。子どもを真ん中に大人たちが見守る、みんなの居場所であってほしいと願っています。