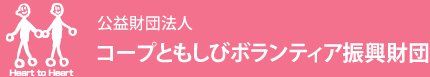石田太介さんのちょっといい話
2025年4月発行/第123号
かぜのさとプレーパーク代表
石田太介さんのちょっといい話
子どもがのびのび遊ぶプレーパークで
豊かな地域を育んでいこう

石田 太介さん(いしだ だいすけさん)
神戸市在住。阪神・淡路大震災をきっかけに市民活動の大切さを知り、大学時代は学生主体の団体にて被災児童対象のキャンプ活動、不登校児童学習支援活動などを行う。その後、プレーパークに出会い、西宮市で常駐プレーリーダーを経験。2022年より[かぜのさとプレーパーク](灘区)を設立し、毎月第一日曜日開催。防災イベントの実施やプレーパーク関連の講座講師なども担う。
冒険遊び場とも呼ばれる「プレーパーク」は、公園によくある禁止事項をなるべく解除し、自由な遊びが体験できるため、子どもたちに大人気。近くにプレーパークがあれば、と思われる方も多いことでしょう。今回ご登場の石田太介さんはよく行く近所の公園で [かぜのさとプレーパーク]を始動。昨年度の「やさしさにありがとうひょうごプロジェクト」の助成団体に選ばれました。プレーパーク立ち上げや子どもとの関わりのヒントについてお聞きしました。
大人に監視されない
遊びは楽しい
私は生まれも育ちも東灘区ですが、中高は県外の学校に進学しました。高3の1月、阪神・淡路大震災が起こり、学校に通えず、しばらく避難所生活を余儀なくされました。このとき気づきましたね。自分の周りには親しい人がおらず、地域とのつながりが希薄だったことを。それから避難所での共同作業に精を出し、多くの人と知りあうことができました。生きていくうえで一番大事な場所は、自分の家の周りやなぁと改めて思いました。そのような経験から地域に根差した活動に興味を持ち、大学時代は被災児童のためのボランティア団体で、レクリエーション活動や不登校児の学習支援などを行いました。当時、学生だけで自主的に社会活動を担う団体がなかったので、とにかく自由で楽しかったですね。おかげで2年、余分に大学生活を送るはめになりました(笑)。
そんななか、プレーパークに関わる出来事がありました。被災児童と一緒にキャンプをしたときのこと。われわれ学生がありったけの情熱を注いで楽しいと思える企画を行う真っ最中に、自分の班の子が「リーダー、これ終わったら遊んでもいい?」と聞いてきたんです。この言葉は衝撃でした。喜んでもらえる遊びをやっていたつもりでしたが、子どもたちはプログラムに付き合ってくれていたんですね。このときから子どもの思い不在の「何かをしてあげる」という大人の一方的な発想に疑問を持ちました。
いろいろ調べていくと日本にはプレーパークという自由な遊び場が関東を中心に増えており、西宮にもプレーパークがあることを知りました。そこではプログラムも何もなく、泥まみれになって遊ぶだけの日もあるなど、普通の公園では見ることのない光景に目を見張りました。そういえば自分も近所の路地や親の目を盗んで墓地に入って遊んだことなど、大人に監視されない子どもだけの空間が楽しかったことを思い出したんです。プレーパークの魅力と少年時代のワクワク感が合致しましたね。その頃の私は社会人でしたが、会社を辞め、西宮のプレーパークに関わることにしました。といってもボランティアではなく、兵庫県の嘱託職員として遊び場に派遣されるもので、専従のリーダーを4年間務めました。
小規模プレーパークは
公園遊びが増えるきっかけに
結婚を機に灘区に移住し、再び会社員になったことでプレーパークとの関わりはほとんどなくなりました。しかし近所の「六甲風の郷公園」には子ども連れでよく出かけました。ここは震災によって倒壊や火災などで焼失した元住宅地で、区画整理事業により防災公園が造成されたところ。当時を知る地域住民も多く、大事な憩いの場として親しまれていました。いつの間にかウォーキングをしているおばあちゃんたちと顔なじみになり、「六甲風の郷公園管理会」の公園清掃にも息子(当時小5)を連れて参加するようになりました。あるとき「この公園でプレーパークという自由な遊び場を開催したい」と言うと、プレーパークをご存じの方がおられ、「管理会」のみなさんが応援団になってくださいました。
2022年10月、[かぜのさとプレーパーク]が始まりました。私たちは木にロープを張ったり、火を使うなどの冒険的な遊びはできませんが、子どもたちや地域の意見を聞き、協力しあいながらプレーパークを実施しています。開催は第一日曜日の午前中(2時間)なので大人の負担が少なく、片付けたら元通りになるシンプルさも自慢です。極力、指導もしません。たとえば、竹とんぼ作りをしていて、失敗しそうだからと手を貸すと、竹を削ることに夢中だったその子は、つまらなくなるかもしれません。夢中になった体験こそ、本当の学びになると思います。ノコギリやカナヅチで試行錯誤しながら工作をする、プールを作るためにバケツに水を汲んでこぼさないように運ぶなど、遊びで得た体験はいざという時の防災力ともなります。
今の時代、公園には禁止看板が多く、「子どもが遊ばない公園」がたくさんできてしまいました。私たちのような小規模プレーパークは無理なく始められ、公園を活性化できる手がかりにもなるので有用だと思います。プレーパークを通して地域の人たちが仲良くなっていけるような、コミュニケーションづくりのお手伝いができればと願っています。