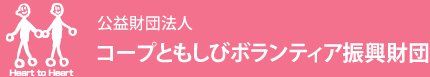赤穂市地域活動連絡協議会の物語り
創造 -子どもたちが安らげる場所を目指して-
コープこうべ職員 長谷川 善久
赤穂市地域活動連絡協議会が行っている、あこう子ども食堂は、放課後の子どもたちの居場所を提供されています。
フードバンク関西、フードバンクはりま、コープこうべからの食材支援を中心に、地域住民や飲食店、高校調理部からの食材提供などで運営されています。
代表を務めるのは岩﨑由美子さん。「たくさんの大人が、自分たちのために何かをしてくれる。そのことが子どもたちの心を満たすと思います。子ども食堂に来ることで、学校が楽しくなり、友達とも上手く関われるようになった。そんな声を聞くと、コミュニティの大切さを感じます」と言います。
おいしいものがあって、友達がいて、楽しい時間が過ぎていく。何をするわけでもなく、みんなが笑顔でいられるところ。昔、近所のおっちゃんやおばちゃんに悪いことをして怒られた。そんな「居場所」が、経済的・精神的貧困の特効薬だと感じています。
たくさんの人に共感を持ってもらっている理由を尋ねたところ、「みんながしたかったことを、私が代表してやっているだけ。だから、みんなが助けてくれているんじゃないかな」と笑います。自分ひとりの力では限界がある。でも、たくさんの人に活動を知ってもらい、助けてくれる人に助けてもらう。この輪がどんどん大きくなって、今日に至っている。そして、常に感謝を忘れない。
取材当日も、お米やじゃがいも、カレールウなど、たくさんの差し入れがありました。子ども食堂に来ていた子どもたちの多くは、小学生から中学生になってもボランティアで手伝いに来てくれるそうです。
この日も一人の女の子が奏でるピアノの音色が心地良かったです。私も岩﨑さんの人柄の良さ、人を惹きつける魅力を感じました。
「継続することが大切なんです」と、岩﨑さんは言います。
こうでないというガイドラインはきちんと決めない。大まかなことしか決めない。メンバーの出入りも自由。フレキシブルがモットーだそうです。試行錯誤を繰り返して向かうべき方向を模索する。ただ、メンバーとの話し合いは徹底的に行うそうです。
みんなに大変だねと言われるが、自分自身ではそんなに大変だとは思っていない。「大変なことはしてないです。それにちゃんとしてないですよ」と笑います。「志し」が、かなり高いところにあると感じました。
あこう子ども食堂は、既存の子ども食堂の枠にとらわれない、全く新しいこども食堂になっていく。まだまだ先にある、岩﨑さんが目指すゴールを目指して。これからもたくさんの人の協力で、あこう子ども食堂は素晴らしい居場所になっていくと感じました。
昭和の香りがする「お母ちゃん」の笑顔がとても印象的で、本当に素敵な居場所でした。
認知症予防のための効果的な運動とその実践講座→開催延期しました
認知症予防に対する効果的な運動について実践・研究している講師から、最新の情報を聞ける学習会です。
認知機能低下を予防するための効果的な運動療法についてのお話と、簡単なトレーニング体験ができます。トレーニングは楽しく、レクレーションとして取り入れられる内容になっています。
家族の認知症が気になる方、認知症予防の活動をしている方など、関心がある方はぜひご参加ください。
新型コロナ感染拡大により、開催を延期(開催日未定)いたします。
日時:2020年7月31日(金) 13:30~15:00
場所:コープこうべ生活文化センター2階 ホール(会場を変更しました)
研究報告者:大島賢典さん(理学療法士)
丸々まるまる神戸学院大学大学院 臨床運動機能研究室
丸々まるまる株式会社 エブリハ
対象者:認知症予防に関心のある方などどなたでも
参加人数:40人
参加費:無料
※大島さんは2019年度に当財団の助成を受けられました。現在、理学療法士及び介護施設におけるコンサルタントとして活躍するかたわら大学院で介護予防、認知症患者の運動機能について研究中。
詳しくは下記のチラシクリックしてください。
佐藤知子さんのちょっといい話
一般社団法人子育て園ぽかぽか 代表理事
子どもが住みよい社会は誰にとっても住みよい
そんなあたたかい保育をみんなの力で
西宮市在住。大学卒業後、幼稚園、保育
所、渡独などの現場実践を重ねながら得
た自身の経験から「こどもを中心に集う
さまざまな年齢・立場の人々が、それぞ
れの役割を持ちながら、いきいきと生き
る場づくり」を目指して活動。現在は、
「自然なタテヨコのつながりを広げてい
くには?」をテーマに取り組み中。趣味は
旅行。「ぽかぽか」に集う人々の笑顔を
見ることが幸せ。
自身のつらい経験から幼少期のよりよい環境づくりをめざした保育を追求する
佐藤知子さん。オープンマインドなお人柄が助けあいの輪を広げているようです。
2018年には、団体として当財団の助成制度「やさしさにありがとう ひょうごプロジェクト」を受けられた佐藤さんに、保育所開設のいきさつとこれからについてお聞きしました。
人生の出発点である保育を
豊かなものにしよう
私が高校生の頃、いとこが自ら命を絶つという痛ましい出来事がありました。
相談を受けていた私は自分の無力さに落ち込み、はたして何ができたんだろうかと悩みました。そのショックを乗り越える過程で大学では卒業論文で幼児心理学を専攻し、「乳幼児期の環境がこどもに与える影響」というテーマに取り組みました。幼少期の環境を整え、豊かにしていくことが大事であると考え、保育の仕事をしようと決意しました。
幼稚園教諭を4年勤めましたが、その間に、大学で少し学んだシュタイナー教育を思い出し、勉強し始めました。理論についてはその多くに共感するものの、引っかかる部分もありました。日本の価値観や慣習がそうさせたのかもしれませんが、どうしても疑問を解決したくて、シュタイナー教育の本場、ドイツへの留学を思い立ちました。ドイツ語もしゃべれないのに、無鉄砲ですよね(笑)。
まず、ドイツ語を学ぶため、近くのドイツ語学校を訪ねました。何気なく掲示板を見ると「日本人のお手伝いさん、求む」という現地の求人情報が掲載されていたんです。天啓とはまさにこのこと(笑)。語学も学ばず、そのままドイツへ渡り、1年間、ドイツ人家庭で住み込みで働きながら、日常会話の習得に励みました。
次の年からは、海外からの学生を積極的に受け入れるシュタイナー教育の学校に通って、2年間の修学課程を終えることができました。3年間の海外生活は私の人生において国際感覚や広い視野を養う、いいきっかけになったと思います。
帰国後、シュタイナー教育を実践する小さな園で働くチャンスをいただきました。2年目から園長を引き受けるという思わぬ展開となり、てんてこまいの私を助けてくださったのが仕事の先輩やご近所のシニア世代の方たちでした。私がみなさんをすごく頼りにすることもあってか、園児らがとてもなつき、シニアの方も園児に会うことが楽しみで来園くださっていました。そのような関係が続くことで、自然と地域ぐるみの交流が始まりました。シニアの方たちは必要とされる場所で生きがいを見つけ、子どもたちはさまざまな得意分野を持った大人と触れ合うなど、地域とともに子どもたちを見守る環境はとてもすばらしいと思いました。両親との同居を機に園を辞めることになりましたが、この経験を活かし、自宅で小規模保育施設を始めることにしました。
地域がつながり 共に生きる場づくりを
2003年、西宮市内で0〜3歳まで定員5人の保育ルーム「ぽかぽか」(保育所待機児童施設)を開設しました。この規模だと子どもの多い大家族のようなものだから、自宅でも十分やっていけるんです。私の両親も手伝っていたこともあり、地域のお年寄りも園児に関わりやすかったようですね。父が乳母車を押す姿はご近所の名物でし
た(笑)。その後、市から定員を増やしてほしいと要請され、隣町にある大きな借家に移転。現在、0〜2歳まで定員12人の小規模保育施設「つくし園」を運営しています。
保育事業を始めた当初から可能な限り、発達に困難のあるお子さんを受け入れるなど、地域で共に育つ保育をめざしていますが、そのようなお子さんの特性や能力に応じた、よりきめの細かい支援も必要と考え、児童発達支援「西宮たんぽぽ」を開設しました。現在は、当時空地だった「つくし園」の隣に大家さんの協力で新設いただき、1日定員10人で午前は就学前の児童発達支援事業(クラス)、午後は就学児童の放課後等デイサービスを行っています。
「たんぽぽ」に通うお子さんはまだ小さいですが、保護者の中には「この子は将来自立できるのだろうか」という先の見えない不安に悩んでおられる方も。そこで地域の就労支援事業所と協働し、「施設間のタテのつながりからこどもの将来を考える」シンポジウムを、ともしび財団の「やさしさにありがとうひょうごプロジェクト」助成で
開催することができました。
「実習先のようすがわかり、地域の力を感じた」「見通しを持って考える貴重な体験だった」という感想が寄せられ、地域が自主的につながることの重要性を大いに感じました。今後もこの取り組みを続けたいと思っています。
私たちのテーマに着目され、共感し応援してくださる財団には深く感謝しています。これからもその理念のもと、いろいろな団体が次のステップに進められるよう支援くださればと願っています。