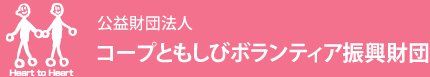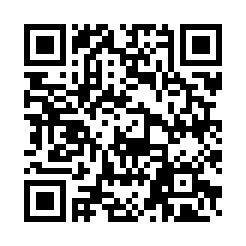丸尾多重子さんのちょっといい話
第2回高校生ともしびボランティア顕彰(アワード)募集→締切りました
「若者のボランティア人材の育成」を実現すべく
昨年度よりスタートした、「高校生ともしびボランティア顕彰(アワード)」。
高校生がボランティア活動を通して心豊かに成長し
次世代の担い手となること、またそこから、世代を超えたネットワークが
うまれることを願っています。
第2回目となる今回は、通常の活動はもちろんのこと、コロナ禍において
思うような活動が出来ない中、状況にあわせて新たにスタートしたり
計画とは形を変えて行った活動などでも、ご応募お待ちしています。
※第1回高校生ともしびボランティア顕彰 顕彰団体はこちら
◆応募資格
兵庫県下の高等学校(全日制・定時制・通信制の高等学校、高等専門学校
中等教育校、養護学校高等部、フリースクール等)に在籍する生徒の皆さんによる
非営利のボランティア活動を行う、生徒会や動活動委員会、サークルなどの
学校に認定された団体であること
※授業としての申請は対象外です。また、1校につき1団体の応募に限ります。
※主な活動以外にボランティア活動を行っている団体も、応募可能です。
(野球部による地域清掃活動 など)
※中高一貫校からの応募の場合は、中学生もご参加いただけます。
※在校生であれば、年齢の上限はありません。
※複数校で構成される団体も応募可能ですが、その場合は監督者が
構成校の教員であることが条件です。
※既に当財団の助成を受けている団体や昨年度の顕彰団体も、応募可能です。
◆顕彰団体数および副賞
15団体程度、1団体につき3万円
◆選考基準
地域や対象者の暮らしを良くすることにつながるボランティア活動や
社会貢献活動を、主体的に行っていること
<選考のポイント>
① 社会貢献度② 創意工夫③学んだこと、感じたこと などを総合的に判断
◆選考方法
申請書受付後に選考基準に基づき、選考委員会にて緩やかな選考を行い
顕彰団体を決定いたします
◆応募期間
2020年10月1日(木)~2020年11月30日(月)
◆スケジュール
・2020年10月1日~2020年11月30日 応募受付
・2020年12月~2021年1月中旬 選考委員会にて申請書を選考
・2021年1月下旬 顕彰決定のお知らせ
◆顕彰決定後について
・交流や発表の機会を設ける予定ですので(2021年3月頃実施予定)
可能であればご参加ください。
・ご希望に応じて、財団が助成しているボランティアグループのご紹介や
財団ホームページにて活動内容をご紹介するなどのサポートを行います。
◆応募方法
指定の申請書に必要事項を記載のうえ、下記宛に郵送にてお送りください。
(メールでの送付は不可)
申請受付締切日: 2020年11月30日 (月) 17時必着
※必ず学校長・指導教員の了承を得てご応募ください。
※顕彰団体に対し、財団からの取材や財団ホームページ・広報物へ
活動内容および写真の掲載などを依頼する場合があります。
※一度ご提出いただいた申請書の返却・差し替えはできません。
※申請書は黒インクか黒ボールペン、又はパソコン入力等で記入してください。
※申請書のご提出前に、必ずコピーをとり、手元に保管しておいてください。
※受付締切日以降に受付することはできませんので、ご注意ください。
※応募に際しご提出いただいた情報は、本顕彰制度をはじめとする
活動支援事業以外の目的では使用いたしません。
◆その他
・選考理由についてのお問い合わせには応じかねますので、予めご了承ください。
・副賞の使用用途について、財団への報告は不要です。
◆申請書の送付先および問い合わせ先
〒658-0081 神戸市東灘区田中町5丁目3-20 生活文化センター西館2F
(公財)コープともしびボランティア振興財団
第2回 高校生ともしびボランティア顕彰(アワード)事務局 宛て
※封筒の表書きに 第2回 高校生ともしびボランティア顕彰(アワード)申請書 と明記してください。
TEL:078-412-3930 (土日祝、年末年始を除く、10:00~17:00)
・募集要項のダウンロードはこちら
・申請書のダウンロードはこちら Word版/PDF版
・チラシのダウンロードはこちら
<後援> 兵庫県教育委員会・兵庫県私立中学高等学校連合会
認知症予防のための効果的な運動とその実践講座の開催を延期します
第4回「やさしさにありがとう ひょうごプロジェクト」助成団体 決定
第4回「やさしさにありがとう ひょうごプロジェクト」選考会を7月8日に開催し、下記の7団体に助成を決定しました。
| 団体名 | プロジェクト名 |
|---|---|
NPO法人ゲートキーパー支援センター |
研修と相談のオンライン化プロジェクト |
高齢者福祉を考える住民の会はこべら |
高齢者の防災・減災拠点になるつどい場づくり |
NPO法人子どものこころと発達支援会あんだんて |
おうちであまねっこプロジェクト |
特定非営利活動法人里地里山問題研究所 |
「獣害から地域を守る」丹波篠山黒豆オーナーによる耕作放棄地の再生と里地里山の価値向上 |
歯科医療サポートセンター |
楽しくお口のトレーニングをしよう ~子どもの健康的な口腔機能を育成~ |
宝塚視力障害者協会 |
コロナと障害者 in たからづか2020 |
特定非営利活動法人つどい場さくらちゃん |
「集えない」「触られない」を越えた“まじくり”の実践 -ポストコロナに向けた新型「つどい場」事業 |
過去の助成団体はこちら
鬼澤康弘さんのちょっといい話
生活協同組合コープこうべ 環境推進統括
脱プラスチックのシンボル「マイバッグ」は
誰もが楽しめるエコなライフスタイルです
川西市在住。大学時代、トルコ共和国の
歴史を研究するため、約2か月トルコ
全土を放浪し、隣接国すべての国境を
訪ねる。99年度入所。宅配、本部など
数所属を経験し、2019年6月より現部署。
「世界を旅し、見識を深めた経験が、
社会事業に熱心なコープこうべの入所に
つながったのかも。環境問題はライフワーク
でもあるので力が入ります」。
趣味はトライアスロン(毎年大会出場)
「昔は手提げかごを持参して買い物したものよ」と懐かしがるのは昭和の世代。
令和のいま、さまざまな年代がお気に入りのマイバッグに、話の花を咲かせます。
大量の使い捨てレジ袋から脱却し、マイバッグが定着するまでには先陣ともいえる
コープこうべの粘り強い運動がありました。
これまでの歴史とこれからについて鬼澤康弘さんにお聞きしました。
マイバッグ運動は
時代とともに進化した
2020年7月1日からレジ袋の有料化が義務付けられたのをご存知でしょうか。
これは使い捨てプラスチックによる環境への負荷を低減するために省令が改正された
ものですが、遡ること42年前(1978年)すでにコープこうべでは「買い物袋再利用
運動」というプラスチックの使用を減らす運動が始まっていました。
70年代といえば、オイルショックの影響で品薄の不安から、トイレットペーパーや
洗剤などの買い占めが多発し、社会が大混乱した時代です。
このような大量消費のライフスタイルを見直し、モノを大切にしようという反省を基に
進めた取り組みのひとつがレジ袋の再利用運動でした。
当時のしくみは使用済みのコープのレジ袋を再利用するとポイントがたまり
買い物代金が値引きされるというもの。
できることからの取り組みでしたが、徐々に賛同者が増えていきましたね。
1991年には「買い物袋再利用運動」からどんな袋でもOKの「買い物袋持参運動」と
なりました。
その次の転機は阪神・淡路大震災が起きた1995年です。
震災による大量の瓦礫やごみが、改めて資源の大切さを考え、シンプルなライフスタイルを目指す大きなきっかけとなり、同年6月からレジ袋の有料化に踏み切ったのです。
金額は今と同じ5円。レジで支払うのではなく、サッカー台(荷造りスペース)に
設置した代金箱にお金を入れるセルフ方式のため、組合員にとっては受け入れやすい仕組みだったようです。ただ、5円玉の両替でレジが煩雑になるとか、代金の入れ忘れなど少なからず課題はありました。
マイバッグ運動が大きく前進したのは2007年。
レジ袋代金をレジでお支払いただく精算方式へと転換した年です。
前年に成立した「改正容器包装リサイクル法」がレジ袋の削減を焦点にしていたので、
これが追い風になったといえます。
この年、コープこうべは先進性と約30年間のレジ袋削減運動が評価され、
「容器包装3R推進 環境大臣賞最優秀賞」を受賞しました。
コープこうべにおけるマイバッグ持参率は1994年の14%に始まり、1995年は77%、
2007年は87%、それ以降は約90%をキープしています。
持参率の上昇とともに、マイバッグも多様化し、おしゃれに楽しむ人が増えてきました。マイバッグは暮らしに密着したシンボリックな環境運動といえますね。
いただいたレジ袋代金は環境活動に全額活用するなど、コープこうべらしい取り組みも
一方で行っています。例えば、「食と環境」に関する学習会やコープの森・社家郷山(西宮市)の森林整備、新加入組合員にお渡しするマイバッグの製作等の費用として活用し、「見えるカタチ」で環境活動に貢献しています。
〝NEXT〞を合言葉に
もっと環境にいいことを
マイバッグが広く浸透してきたとはいえ、持参率90%前後で頭打ちになっているのが実情です。そこで今年6月から「マイバッグ運動NEXT」として、ギアを上げた脱プラスチックの取り組みをスタートしました。コンセプトは3つ。
1つめは【減らす】。無料でお渡ししていた衣料品や住居関連のレジ袋を有料化し、
生鮮品についてはレジで職員がポリ袋に入れるのをやめ、セルフで備え付けのポリ袋を
使用していただくことで更なる削減を目指します。
2つめは【増やす】。マイバッグをお持ちでない方に「レンタルバッグ※1」(無料)を案内し、袋の必要性を実感していただくことで持参率アップを図ります。
2000年から展開していますが、さらに強化します。
また一部店舗では、家に余っている紙袋を店に持ち寄っていただき、レジ袋代わりに使う「シェアバッグ※2」も実施し好評をいただいています。生協らしい、助け合いのしくみにつながることを期待しています。
3つめは【広める】。
マイバッグ運動がなぜ始まり、どのような変遷を経て、今後どう発展させていくのか。
そのストーリーをポスターやリーフレットを通して伝え、使い捨てプラスチックや
海洋ごみなど、身近な問題について考え、行動するきっかけにしていただきたいと思います。
学校では「SDGs(持続可能な開発目標)」など世界を意識した環境教育が行われています。子ども世代はもっと素直に環境保全の考えを受け入れていくでしょう。そのためにもいま私たち大人がどのような方向に社会を導くのか、真剣に考えたいですね。
※1、※2…一時的に利用を休止している場合があります。
2021年度ボランティア活動助成説明会→終了しました
(公財)コープともしびボランティア振興財団では、市民がお互いに支え合い、やさしさと思いやりに満ちた地域社会の形成を目指すボランティア活動を応援する助成を行っています。
2021年度助成金申請にあたっての説明会を、下記のとおり県内9カ所で行います。
お申し込みはこちらから
<会場により残席あり。詳しくはページ下の表をご覧ください。>
助成金申請には、説明会へのご参加が必須となっています。
申請を希望されるグループは、下記いずれかの説明会へ必ずご参加ください。
※法人格をお持ちの団体は対象外です
※コロナの状況によっては、オンライン説明会に移行する場合があります
※お一人で複数グループの参加を兼ねることは出来ません
<お申込み方法>
説明会チラシ裏面の参加申込書に必要事項をご記入のうえ
下記お申し込み先までご連絡ください。
(時節柄、参加者は1グループ1名まで)
※インターネットからもお申込みできます。
| 日時 | 会場 | 残席 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020年10月30日(金) 13:30~15:30 |
神戸市立総合福祉センター 4階 第5会議室 | 満席 |
| 2 | 2020年11月4日(水) 13:30~15:30 |
姫路じばさんびる 6階 601会議室 | 満席 |
| 3 | 2020年11月5日(木) 13:30~15:30 |
ピピアめふ 5階会議室A・B | 満席 |
| 4 | 2020年11月9日(月) 13:30~15:30 |
篠山市民センター 1階多目的ルーム1 | 満席 |
| 5 | 2020年11月10日(火) 13:30~15:30 |
コープこうべ生活文化センター西館2階 小会議室 | 満席 |
| 6 | 2020年11月18日(水) 13:30~15:30 |
複合型交流拠点ウィズあかし 学習室 7階704 | 2人 |
| 7 | 2020年11月19日(木) 13:30~15:30 |
西宮市民会館 4階401会議室 | 3人 |
| 8 | 2020年11月24日(火) 13:30~15:30 |
コープこうべ協同学苑 2階研修室A | 満席 |
| 9 | 2020年11月28日(土)
10:00~12:00 |
コープこうべ生活文化センター 2階ホール | 4人 |
※台風、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止や延期または会場など、予定を変更する場合があります。開催状況は当財団ホームページにてお知らせします。ご参加の前には必ずホームページをご確認ください。ホームページが閲覧できない場合は、当財団までお電話(078-412-3930)でお問い合わせください。
◆2021年度 ボランティア活動助成について◆
- 対象:兵庫県内で継続的に活動(年間10回以上※1、申請時に半年以上の活動実績があること)する福祉・環境などのボランティアグループ(または個人)。法人格を持つ団体は対象外
- 助成金額:団体30万円、個人3万円、きらり助成1.5万円(いずれも上限)
- 対象期間:2021年4月1日(木)~2022年3月31日(木)
- 募集期間:2020年10月30日(金)~2021年1月7日(木)必着
- 助成決定:2021年3月下旬~4月初旬
※1.2020年度に限り、コロナの影響で活動回数が10回に満たなくでも構いません
問い合わせ・申込み
(公財)コープともしびボランティア振興財団
電話:078-412-3930 FAX:078-412-3871
神戸星城高等学校コンピュータ部の物語り
勇躍 -新長田から日本、そして世界へ-
コープこうべ職員 長谷川 善久
神戸星城高校のコンピュータ部はインターネット上で店巡りの疑似体験ができる「バーチャル商店街」を制作し、新聞やニュースで有名になった。あれから6年が経つが、新たなチャレンジに向かっている。
神戸星城高校の前身の神戸女子商業高校は、JR新長田駅南の大正筋商店街にあった。しかし1995年の阪神・淡路大震災に遭い、同市須磨区に移転。校名も神戸星城高等学校となり、共学になった。
震災後、同部の顧問、延原宏教諭は岡山の公立高校に移り、13年後に神戸に戻って来た。「もともと決まっていた転勤とはいえ、被災した生徒たちに何もできず神戸を離れたことが、非常に心残りだったんです」と語る。
久しぶりの故郷である大正筋商店街は、高齢化が進み、かつての賑わいもなかった。生徒たちがいなくなって淋しそうな商店街。一念発起し、彼は地域と生徒を繫げる復興を目指す。
バーチャル商店街は、インターネット上であたかも商店街を歩いているような疑似体験ができる。5メートルおきに景色が変わり、各店舗をクリックすると、営業時間や店舗情報などが表示され、買い物も出来る。店主と共同でCM作成も行い、完成度の高いウェブサイトだ。
すでに大正筋商店街、六間道商店街、本町街商店街、西神戸センター街の4つのバーチャル化を終えている。新しい取り組みとして、新長田再開発で建設予定の合同庁舎職員をターゲットにした地域情報誌「FULLBUL(フルブル)」の製作も始めた。地域貢献の一環として、近隣地域住民対象のパソコン教室も精力的に行っている。
取材当日もパソコン教室を覗かせてもらった。生徒たちが主体となって、行われていた。生徒たちが自発的に企画・立案し、実行し、検証を繰り返す。P(プラン)D(ドゥ)C(チェック)A(アクション)サイクルが出来上がっている。生徒たちは、バーチャル商店街制作を通して、情報収集能力や対面技術を取得し、ビジネスセンスとコミュニケーション能力を身に付けたのであろう。頻繁に行われたグループディスカッションで培われたメタ認知(客観的自己分析)能力も高い。地域活性化の手助けが出来ているという達成感が、生徒たちをより積極的に成長させている。
「公立と私立の学校は違うんです」と彼は言う。
神戸星城高校は私立学校で、生徒の居住エリアが公立学校より広い。そのため近隣地域出身の生徒は公立学校よりも少なく、近隣地域との関係性が希薄になりやすい。バーチャル商店街や地域情報誌の制作、パソコン教室を通して地域貢献をする。それをアイデンティティーとし、次のチャレンジのモチベーションへ繫げる。地元愛がベースの「延原イズム」が継承され、延原ファミリーがどんどん巣立っている。
ICT技術を活かすために企業の開発部門に進む生徒も多く、地域活性化を担うために自治体への貢献を希望する生徒もいる。
最近は、教え子から連絡はあるものの忙しくて、なかなか顔を見せに帰って来ない。そんな状況を淋しく思うが、嬉しくも思う。研究・開発に没頭している証拠だと誇りに思う。
新長田の商店街を元気にしてきた教え子たちが日本を元気にし、世界で活躍する日を確信している。彼の強いまなざしを見ていると、その日がそう遠くない未来だと思えた。
赤穂市地域活動連絡協議会の物語り
創造 -子どもたちが安らげる場所を目指して-
コープこうべ職員 長谷川 善久
赤穂市地域活動連絡協議会が行っている、あこう子ども食堂は、放課後の子どもたちの居場所を提供されています。
フードバンク関西、フードバンクはりま、コープこうべからの食材支援を中心に、地域住民や飲食店、高校調理部からの食材提供などで運営されています。
代表を務めるのは岩﨑由美子さん。「たくさんの大人が、自分たちのために何かをしてくれる。そのことが子どもたちの心を満たすと思います。子ども食堂に来ることで、学校が楽しくなり、友達とも上手く関われるようになった。そんな声を聞くと、コミュニティの大切さを感じます」と言います。
おいしいものがあって、友達がいて、楽しい時間が過ぎていく。何をするわけでもなく、みんなが笑顔でいられるところ。昔、近所のおっちゃんやおばちゃんに悪いことをして怒られた。そんな「居場所」が、経済的・精神的貧困の特効薬だと感じています。
たくさんの人に共感を持ってもらっている理由を尋ねたところ、「みんながしたかったことを、私が代表してやっているだけ。だから、みんなが助けてくれているんじゃないかな」と笑います。自分ひとりの力では限界がある。でも、たくさんの人に活動を知ってもらい、助けてくれる人に助けてもらう。この輪がどんどん大きくなって、今日に至っている。そして、常に感謝を忘れない。
取材当日も、お米やじゃがいも、カレールウなど、たくさんの差し入れがありました。子ども食堂に来ていた子どもたちの多くは、小学生から中学生になってもボランティアで手伝いに来てくれるそうです。
この日も一人の女の子が奏でるピアノの音色が心地良かったです。私も岩﨑さんの人柄の良さ、人を惹きつける魅力を感じました。
「継続することが大切なんです」と、岩﨑さんは言います。
こうでないというガイドラインはきちんと決めない。大まかなことしか決めない。メンバーの出入りも自由。フレキシブルがモットーだそうです。試行錯誤を繰り返して向かうべき方向を模索する。ただ、メンバーとの話し合いは徹底的に行うそうです。
みんなに大変だねと言われるが、自分自身ではそんなに大変だとは思っていない。「大変なことはしてないです。それにちゃんとしてないですよ」と笑います。「志し」が、かなり高いところにあると感じました。
あこう子ども食堂は、既存の子ども食堂の枠にとらわれない、全く新しいこども食堂になっていく。まだまだ先にある、岩﨑さんが目指すゴールを目指して。これからもたくさんの人の協力で、あこう子ども食堂は素晴らしい居場所になっていくと感じました。
昭和の香りがする「お母ちゃん」の笑顔がとても印象的で、本当に素敵な居場所でした。
認知症予防のための効果的な運動とその実践講座→開催延期しました
認知症予防に対する効果的な運動について実践・研究している講師から、最新の情報を聞ける学習会です。
認知機能低下を予防するための効果的な運動療法についてのお話と、簡単なトレーニング体験ができます。トレーニングは楽しく、レクレーションとして取り入れられる内容になっています。
家族の認知症が気になる方、認知症予防の活動をしている方など、関心がある方はぜひご参加ください。
新型コロナ感染拡大により、開催を延期(開催日未定)いたします。
日時:2020年7月31日(金) 13:30~15:00
場所:コープこうべ生活文化センター2階 ホール(会場を変更しました)
研究報告者:大島賢典さん(理学療法士)
丸々まるまる神戸学院大学大学院 臨床運動機能研究室
丸々まるまる株式会社 エブリハ
対象者:認知症予防に関心のある方などどなたでも
参加人数:40人
参加費:無料
※大島さんは2019年度に当財団の助成を受けられました。現在、理学療法士及び介護施設におけるコンサルタントとして活躍するかたわら大学院で介護予防、認知症患者の運動機能について研究中。
詳しくは下記のチラシクリックしてください。
佐藤知子さんのちょっといい話
一般社団法人子育て園ぽかぽか 代表理事
子どもが住みよい社会は誰にとっても住みよい
そんなあたたかい保育をみんなの力で
西宮市在住。大学卒業後、幼稚園、保育
所、渡独などの現場実践を重ねながら得
た自身の経験から「こどもを中心に集う
さまざまな年齢・立場の人々が、それぞ
れの役割を持ちながら、いきいきと生き
る場づくり」を目指して活動。現在は、
「自然なタテヨコのつながりを広げてい
くには?」をテーマに取り組み中。趣味は
旅行。「ぽかぽか」に集う人々の笑顔を
見ることが幸せ。
自身のつらい経験から幼少期のよりよい環境づくりをめざした保育を追求する
佐藤知子さん。オープンマインドなお人柄が助けあいの輪を広げているようです。
2018年には、団体として当財団の助成制度「やさしさにありがとう ひょうごプロジェクト」を受けられた佐藤さんに、保育所開設のいきさつとこれからについてお聞きしました。
人生の出発点である保育を
豊かなものにしよう
私が高校生の頃、いとこが自ら命を絶つという痛ましい出来事がありました。
相談を受けていた私は自分の無力さに落ち込み、はたして何ができたんだろうかと悩みました。そのショックを乗り越える過程で大学では卒業論文で幼児心理学を専攻し、「乳幼児期の環境がこどもに与える影響」というテーマに取り組みました。幼少期の環境を整え、豊かにしていくことが大事であると考え、保育の仕事をしようと決意しました。
幼稚園教諭を4年勤めましたが、その間に、大学で少し学んだシュタイナー教育を思い出し、勉強し始めました。理論についてはその多くに共感するものの、引っかかる部分もありました。日本の価値観や慣習がそうさせたのかもしれませんが、どうしても疑問を解決したくて、シュタイナー教育の本場、ドイツへの留学を思い立ちました。ドイツ語もしゃべれないのに、無鉄砲ですよね(笑)。
まず、ドイツ語を学ぶため、近くのドイツ語学校を訪ねました。何気なく掲示板を見ると「日本人のお手伝いさん、求む」という現地の求人情報が掲載されていたんです。天啓とはまさにこのこと(笑)。語学も学ばず、そのままドイツへ渡り、1年間、ドイツ人家庭で住み込みで働きながら、日常会話の習得に励みました。
次の年からは、海外からの学生を積極的に受け入れるシュタイナー教育の学校に通って、2年間の修学課程を終えることができました。3年間の海外生活は私の人生において国際感覚や広い視野を養う、いいきっかけになったと思います。
帰国後、シュタイナー教育を実践する小さな園で働くチャンスをいただきました。2年目から園長を引き受けるという思わぬ展開となり、てんてこまいの私を助けてくださったのが仕事の先輩やご近所のシニア世代の方たちでした。私がみなさんをすごく頼りにすることもあってか、園児らがとてもなつき、シニアの方も園児に会うことが楽しみで来園くださっていました。そのような関係が続くことで、自然と地域ぐるみの交流が始まりました。シニアの方たちは必要とされる場所で生きがいを見つけ、子どもたちはさまざまな得意分野を持った大人と触れ合うなど、地域とともに子どもたちを見守る環境はとてもすばらしいと思いました。両親との同居を機に園を辞めることになりましたが、この経験を活かし、自宅で小規模保育施設を始めることにしました。
地域がつながり 共に生きる場づくりを
2003年、西宮市内で0〜3歳まで定員5人の保育ルーム「ぽかぽか」(保育所待機児童施設)を開設しました。この規模だと子どもの多い大家族のようなものだから、自宅でも十分やっていけるんです。私の両親も手伝っていたこともあり、地域のお年寄りも園児に関わりやすかったようですね。父が乳母車を押す姿はご近所の名物でし
た(笑)。その後、市から定員を増やしてほしいと要請され、隣町にある大きな借家に移転。現在、0〜2歳まで定員12人の小規模保育施設「つくし園」を運営しています。
保育事業を始めた当初から可能な限り、発達に困難のあるお子さんを受け入れるなど、地域で共に育つ保育をめざしていますが、そのようなお子さんの特性や能力に応じた、よりきめの細かい支援も必要と考え、児童発達支援「西宮たんぽぽ」を開設しました。現在は、当時空地だった「つくし園」の隣に大家さんの協力で新設いただき、1日定員10人で午前は就学前の児童発達支援事業(クラス)、午後は就学児童の放課後等デイサービスを行っています。
「たんぽぽ」に通うお子さんはまだ小さいですが、保護者の中には「この子は将来自立できるのだろうか」という先の見えない不安に悩んでおられる方も。そこで地域の就労支援事業所と協働し、「施設間のタテのつながりからこどもの将来を考える」シンポジウムを、ともしび財団の「やさしさにありがとうひょうごプロジェクト」助成で
開催することができました。
「実習先のようすがわかり、地域の力を感じた」「見通しを持って考える貴重な体験だった」という感想が寄せられ、地域が自主的につながることの重要性を大いに感じました。今後もこの取り組みを続けたいと思っています。
私たちのテーマに着目され、共感し応援してくださる財団には深く感謝しています。これからもその理念のもと、いろいろな団体が次のステップに進められるよう支援くださればと願っています。
第4回「やさしさにありがとう ひょうごプロジェクト」助成団体募集→締切りました
社会的課題を解決しようとしている、意欲あふれる市民団体を、賛同企業と力を合わせて応援していこうという助成制度です。
今年度は、新型コロナウイルス感染症に対応して、これまでの事業を変更し
新たな支援事業を立ち上げている団体や、既存事業の拡充して取り組んでいる団体にも助成します。
★募集期間:2020年4月1日(水)~6月3日(水)17:00必着
★助成金額:1団体あたり上限50万円
募集要項、申請用紙は こちらへ
☆やさしさにありがとう ひょうごプロジェクト 助成団体募集ちらし☆
馬場正一さんのちょっといい話
社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会事務局次長
兵庫県を地域福祉への参画と協働の先進県に

1965年大分県生まれ。同志社大学
文学部社会学科社会福祉学専攻卒。
兵庫県内の市町社会福祉協議会を経て
90年(社福)兵庫県社会福祉協議会の職員に。
阪神・淡路大震災では災害ボランティア・
NGО支援等を行い、「ひょうごボランタリー
プラザ」の立ち上げにも参画。
地域福祉部長、生活資金部長、企画部長等を歴任。
コープともしびボランティア振興財団理事、
兵庫県ボランティア協会理事等を担う。
「社会福祉協議会の仕事って、知ってますか。社会福祉を協議する組織ですよ。
それも、兵庫県全域を対象にした協議会の仕事って、なかなか奥が深いですよ」。
そう笑顔で語るのは、当財団の理事でもある馬場正一さんです。
兵庫県社協の役割と醍醐味などについてお聞きしました。
社会福祉の道を目指した
さまざまな思い出
私は大分県の国東半島の田舎町で生まれ、大学進学を機に関西に移りました。
大学の専攻は社会福祉ですが、高校の進学指導の先生から当時はまだあまり知られていない社会福祉の道へ進むことに「進路を考えなおしたらどうだ」等、何度か意見をいただいたのを覚えています。
そんな社会福祉に関心を持ったのは幼少期の出来事が原体験のように思います。
両親は家業の豆腐屋の商売で忙しく、私は「おばあちゃん子」として育ちました。
小学生のとき、学校から帰ると、祖母が倒れているのを発見。近所に住む叔父を呼び、祖母の一命を取り留めたことがありました。
祖母が親戚たちの前で「この子は命の恩人だ」と言ってくれたことは今でも忘れません。「誰かの役に立ったんだ、これからも誰かの役に立ちたい」と思った瞬間でした。
大学では「社会福祉学研究会」というサークルに所属し、ゼミで学んだ福祉理論の追求やボランティア活動を行っていました。
ボランティア活動の一つに同年代の筋ジストロフィの男性の車いす介助があったのですが、あるとき彼が松田聖子のコンサートに行きたいと言うので、車いすで会場に向かったところ、専用通路からスムーズに専用席に案内していただけました。バリアフリーがいかに大切であるかを感じた思い出です。
社協が変われば、地域も変わる
地域が変われば、社協も変わる
行政でも民間企業でもない社協のような中間の組織は、自由な立ち位置で福祉の仕事ができると思い、就職活動は社協一本に絞っていました。しかし、なかなか募集がなく、卒業直前の2月にようやく、県内のある市町社協の募集があり、採用試験に合格することができました。
当時の社協の仕事は、老人クラブや遺族会などの団体事務が半分、葬祭壇の貸出や結婚式場の運営が半分と、目立った地域福祉活動はありませんでした。
「それなら自分がやってやろう」と意気込み、理解のある地域住民と連携し、福祉委員の設置や給食サービスの実施、社協会員会費制度を導入しました。
よそから来た若者が頑張っていると温かく応援してくださる人たちと、社協で働く先輩からの「石の上にも三年」という言葉が心の支えでした。
私が仕事でこだわってきたことは二つあります。
一つ目は、社協は「住民主体の原則」を持っているので、こちらの呼びかけを強制するのではなく、現場の感性や意見を尊重すること。
二つ目は連絡調整に心を砕くことです。社協の最大の役割は何かと問われたら、連絡調整だと思います。これは「中間支援」という言葉に置き換えられますが、いろいろな団体を対等につなぎ、「WIN -WIN」の双方プラスの関係を築いていくこと。三方良しという言葉がありますが、つなげることによって「よい化学反応」を起こしたいです。
その触媒の役割が社協だと思っています。
「ほっとかへんネット」で地域のSOSをキャッチしよう
約10年前、NHKが報道した「無縁社会」の実態は私たちに大きな衝撃を与えました。
孤独な高齢者や引きこもる若者・中年、ワンオペ育児に悩む母親など、希薄な人間関係による現代社会の問題が浮き彫りにされました。
これらは誰もが避けられない身近なテーマです。
この状況をなんとかしようと兵庫県社協では「ストップ・ザ・無縁社会」全県キャンペーンを平成24年に提唱し、様々な啓発活動に取り組んでいます。
翌年から、県内の社会福祉法人をつなげる「社会福祉法人連絡協議会(ほっとかへんネット)」の立ち上げに着手しました。
これまで、市区町域では特養や保育など、施設の種別ごとの会合はあっても、「社会福祉法人」というくくりで集まる機会はありませんでした。この取り組みでは多種多様な地域資源がつながり、市区町域でのセーフティネットを展開していくことを目標にしています。「ほっとかへん」を合言葉に、居場所づくりやごみ屋敷問題の解決など、地域の特性に応じた活動が行われています。
そのような地域の課題解決をサポートする組織として、ともしび財団も意義深い事業を行っています。県内にはたくさんの助成団体があり、それぞれのミッションに基づいて活動しています。ネットワークがあれば、重複している部分や着手できていない分野などが解消され、よりきめ細かな支援が実現できるかもしれません。
それぞれの財団の持ち味を活かしつつ、協働できるような仕掛けを考えてみたいですね。